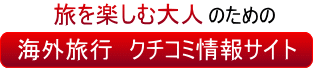-切られた島-

ある国の、西の外れに、ちょっと大きめの島がありました。
南北に細長い島で、横幅は大してないのですが、長さはわりとあったため、船で回り込もう
とすると、昔は何日もかかりました。
そこで人々は、一番幅の狭い場所を選んで船を陸に上げ、丸太に乗せて牛に引かせ、
陸地を進みました。
そうして船を島の反対側まで運んでいたのです。
もちろん大変な仕事でしたが、島を回り込むよりはずっとましだったのでしょう。
その頃のことは、今も地名になって残っています。
ある時代に、一人の殿様が命じました。
「地面を掘って水をひき、船が通れる道を作れ。」
そこで、一番掘る距離が短い所を選んで、水路作りが行われました。
昔のことなので、ほとんど人の力で行われた大変な工事でしたが、おかげで船は
もう丘を越えなくてもよくなり、東側から西側まで、島を横断して反対側の海に
出られるようになりました。
 その もっと後の時代に、島に 海軍が配備されました。
海軍は、島のどちら側にもすばやく軍艦を移動させたいと考えましたが、昔の水路は幅も細くて水深も浅く、大きな軍艦を通すにはちょっと無理がありました。
そこで少し離れた場所に、もっと大きな、第二の水路を作ったのです。
この水路のおかげで、軍艦が島を横断できるようになりました。
また、一般の人々にも使用が認められたおかげで、人や物の行き来が活発になり、島の経済も発展しました。
九州の西に浮かぶ島、対馬(つしま)。

もとはひとつにつながった島でしたが、今の対馬は二本の水路で 三つに切られており、上にはそれぞれ 橋が架かっていて、車で通ることができます。
江戸時代に殿様が作った水路は 大船越瀬戸(おおふなこしせと)と呼ばれ、後に少し広げられて今も使われています。
後にできた大きな水路は 万関瀬戸(まんぜきせと)と呼ばれ、そこに架かる 万関橋(まんぜきばし)の上からは、海をのぞんだ絶景が楽しめるといいます。
対馬を訪れる際には、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょう。
【ハカセの... もうちょっと知りたい!】
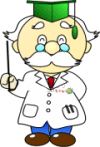 ある国: 日本のことです。 ある国: 日本のことです。
南北に細長い島: 対馬(つしま)。長崎県では最大の島。
日本からは100km以上離れていますが、韓国へは50kmほどです。
そのため、古くから外国との交流や争いの場所となってきました。
大きさは南北に82km、東西に18kmほどですが、100以上の小さな島を持ち、リアス式海岸が発達しているため、海岸線の総延長は915kmにも及ぶそうです。
地名になって: 小船越(こふなこし)、大船越(おおふなこし)という地名が
残っています。小さな船は小船越、大きな船は大船越で陸を越えたそうです。
小船越には水路は作られていません。
殿様:対馬の21代藩主、宋義真(そう よしざね)です。
水路作り:1672年頃に、最初の水路である大船渡瀬戸ができたそうです。
もっと後の時代:明治時代。
海軍: 大日本帝国海軍。
第二の水路: 1900年に万関瀬戸ができました(長さ約500m)。大船渡瀬戸
より2kmほど北にあります。
三つに切られて: 万関瀬戸より北が上島(かみじま)、南を下島(しもじま)と呼ばれます。
橋が架かって: 大船渡瀬戸には、大船渡橋(おおふなとばし)万関瀬戸には万関橋
(まんぜきばし)が架かっています。
◆オマケの話:
現在万関瀬戸に架かる万関橋は、三代目です。
最初は1900年、次に1956年、今の三代目は1996年に架けられました。
万関瀬戸は、出来た当時は幅25m、深さ3m程度でした。土ではなく岩盤だったため、
ダイナマイトや人力で掘り進む難工事だったそうです。
昭和50年に幅40m、深さ4.5mに拡張されました。
度重なる橋の架け直しや運河の拡張は、対馬にとってこの運河がいかに重要な
ものかを物語っていますね。
|
|
|
|